親族の介護を手伝うことになり、現状の把握と経緯を確認。
介護対象者は70代老夫婦の旦那さん。
旦那さんが寝たきり状態になって、要介護1から要介護5へと変更。
ケアマネジャーさん、ヘルパーさんたちと協力しながら自宅介護とショートステイを繰り返す。
その間に、特養施設の入所申込をして、施設見学に行ったり、自宅面談したりと打ち合わせを経て、何とか本入所が決定。
契約も終わり、他施設に断りの連絡を入れ、いったんの一区切り・・・?

施設の利用料金を知るということ
なんとか無事に特養施設の入所も決まって、契約も終わりました。
これで介護生活から解放される!小休止だ!
と思いきや・・・予想してなかったことが起きて・・・。
ということで、まだまだ介護日記は続きます。
とりあえず今回は、特養施設の利用料金について書きたいと思います。
こういうのって、実際に自分自身で触れないと知ることがなかったことなので勉強になりました。
今後の高齢化社会において、施設での介護は避けて通れないと思います。
老人ホームは高い!と勝手なイメージで考えていましたが、「なぜ、高いのか」という理由をきちんと知ることで、入れる施設、入れない施設を把握することができます。
高い施設は無理、できるだけ安い施設に入れたいと言う前に、どうしたら安い施設に入れられるのかを調べた方が良いです。
先に少しだけ結論を言うと、お金持ちはそれ相応の金額を払わないと施設に入れない仕組みになっています。
老人ホームの種類を知る
まず、老人ホームには大きく分けて民間施設と公的施設の2種類があります。
そこから更に、入居する方の介護度や費用、認知症の有無などによって、いくつかのタイプの施設に分けられます。
| 種類 | 自立 | 要支援1~2 | 要介護1~2 | 要介護3~5 | 認知症 |
| 1.介護付き有料老人ホーム | △ | △ | ○ | ○ | ○ |
| 2.住宅型有料老人ホーム | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3.サービス付き高齢者向け住宅 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4.グループホーム | × | △ | ○ | ○ | ○ |
| 5.ケアハウス | ○ | ○ | △ | △ | △ |
| 6.特別養護老人ホーム | × | × | × | ○ | ○ |
| 7.介護老人保健施設 | × | × | ○ | ○ | ○ |
| 8.介護医療型医療施設 | × | × | ○ | ○ | ○ |
民間施設→1~4、公的施設→5~8
○:受入れ可 △:施設によって受入れ可 ×:受入れ不可
一般的に、「老人ホームは高すぎる!」と言われる所以になっているのは、民間施設の方だと思われます。
民間施設は、家賃・食費・入居費用は各施設が個別に設定しているためですね。
料金設定はピンキリですが、けっこう高めです。
対して公的施設の方は、料金も安めに設定されています。
ただし、要介護認定が必須となります。
今回、本入所が決まったのは、特別養護老人ホーム(通称:特養)なので、公的施設で料金も安め。
ただし、要介護は3以上でないと入所対象になりません。(要介護1~2でも入所は可能ですが、自治体から特別な許可が必要となります)
入所した旦那さんは、要介護5(認知症もあり)だったので、条件を満たしていたというわけです。
特養はその性質上、かなり人気が高いです。
低価格で看取りまで対応してもらえて、ユニット型タイプの部屋もあって、手厚い介護サービスが受けれます。
考えることは誰しも同じで、終の棲家としても人気な特養は、順番待ちの待機者もかなり多めです。
そこらへんについては、過去の記事で書いてあります。

施設の料金に関して
さて、ここからは特養の料金に関してです。
今回、このようなことがなければ、自分自身も知らないままでした。
特養施設の利用料金の重要ポイントは以下になります。
- 要介護度で料金が変わる。(1~5)
- 介護保険負担割合証が何割負担かで料金が変わる。(1~3割)
- 負担限度額認定証の段階数で料金が変わる。(1~4段階)
利用料金が決定する大きな変動としては上記3つになると思います。
介護保険負担割合証の負担割合でも料金は数万円ほど変わりますが、一番大きく変わるのは「負担限度額認定証が何段階であるか?」です。
この負担限度額認定がとても厄介でして、何をもってこの限度額認定の段階が決まるのかというと、
になります。
公的年金収入には非課税年金を含みます。

え・・・預貯金額!?
と思った人もいるかと思います。
そうなんです、預貯金額も対象となるので調べられてしまうのです。
要は、お金持ちは施設料金が高くなるし、お金がない人は安くなるということです。
| 公的年金収入等 | 預貯金額 | |
| 第1段階 | 年金収入等80万円以下 | 下記以下の場合 |
| 第2段階 | 年金収入等80万円以下 | 単身650万円、夫婦1,650万円以下 |
| 第3段階① | 年金収入等80万円超120万円以下 | 単身550万円、夫婦1,550万円以下 |
| 第3段階② | 年金収入等120万超 | 単身500万円、夫婦1,500万円以下 |
| 第4段階 | 年金収入等120万超 | 上記以上の場合 |
この負担限度額については令和3年(2021年)8月から変更になったようです。
以前はもっと条件が甘めに設定されていました。(厚生労働省の資料より)
第4段階は実際の所、負担限度額認定証という物は発行してもらえません。
あなたは生活余裕でしょ?自分のお金で施設を利用してね、ということです。
まあ、この負担限度額表も将来的には更に変更がかかるかもしれません。
どちらにせよ、将来的に年金はほとんどもらえないだろう、将来的に貯金もほぼないだろうという人間にとっては大変助かる制度ではあります。
今回、旦那さんが特養施設を利用するにあたって、どれくらいの月額だったのかは言えませんが、高齢者はお金がないって言いながら、お金をたくさん持っているということがデフォルトなのだということはよく分かりました。
預貯金額はどこまで調べられるのか
負担限度額認定証は区役所等で発行してもらうのですが、申請にいくと預貯金額を全部調べられます。
なので、事前に自分たちが負担限度額認定証のどの段階に該当するかを調べておく必要があると思います。
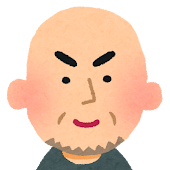
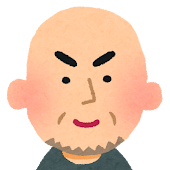
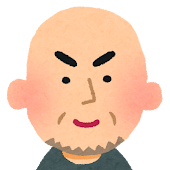
調べるまでもなく、お金がめっちゃあるから第4段階だろう。
だから区役所も行かない。
ということなら申請に行かなくても大丈夫です。
結局、第4段階なら申請しても何も発行してもらえませんし。
ということで、下記に預貯金額の対象となるものをまとめました。
2024年末現在のところの話であり、今後変わる可能性もあると思います。
- 預貯金(普通・定期)
- 有価証券(株式・国債・地方債・社債など)
- 金・銀(積立購入含む)
- 投資信託
- 箪笥貯金(自己申告制)
- 生命保険
- 自動車
- 腕時計
- 宝石
- 時価評価額の把握が難しい貴金属、絵画、骨董品、家財
預貯金の対象を見てみれば、自分の資産をどう形にして残すか、というのも見えてくるのではないかと思います。
預貯金等に含まれないもの一覧を見てみると、まさしくお金持ちが好んで購入するもの一覧ですもんね。
そういうことなんでしょう。
施設の利用料金に関して その他
要介護度がいくつで、介護保険負担割合証が何割で、負担限度額認定証が何段階でと見やすく分かれているので、とても便利です。
しかし、これで特養の月額全てが把握できるわけではありません。
他にも施設ごとに散髪代や歯医者代等の料金が発生したりと雑費がいくらかあります。
今回の自分の場合でいうと、散髪利用代(選べる)、歯医者利用代(選べる)、薬代(必須)が月々の施設利用料金にプラスされて請求される感じでした。
特養は人気です。
今回の施設探しのときに調べた感じでは、各施設の平均は100床くらいでした。
その数に対して申請者は何倍もいます。多ければ10倍以上います。
高齢者のほとんどは、1円でも安い方に流れる傾向があるので、どうしても安い施設に待機人数が増えます。
そのため、あらかじめ利用料金などを自分たちで把握しておいて、介護対象者の年金内の金額で施設を利用できると分かっていれば、少し高めの施設を狙うのもありだと思います。
利用料金が高めの施設は、待機人数も少な目です。
待機人数が少ないということは、比較的早く特養施設に入所ができるので介護の負担が減るということです。
施設代が安いところを狙い、介護対象者の年金を少しでも自分の生活に充てて生活に潤いを持たせるために待機時間を長くするのか、介護対象者の年金を全て使用してでも早急に介護負担を減らすのか。
何を天秤にかけるか、ということですね。
次回は、特養入所後に発生した新たに問題について!


コメントを残す